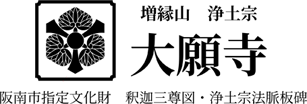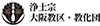七五三祀り 仏前結婚式

七五三祀り
3歳の男の子・女の子「髪置きの儀」
5歳の男の子「袴着(はかまぎ)の儀」
7歳の女の子「帯解(おびとき)の儀」
七五三の由来には諸説ありますが、平安時代の頃から宮中で行われていた3つの儀式が基になっているそうです。現代に比べて医療の発達が未熟で衛生面もよくなかった昔は、子どもの死亡率がとても高く「7歳までは神のうち(神の子)」として扱われ、7歳になって初人として一人前であると認められていました。
子どもが無事に育つことは大きな喜びであり、親として健やかな成長を願わずにはいられないものでした。それゆえ、3歳、5歳、7歳の節目に成長を神様に感謝し、お祝いをしたことが七五三の由来です。
3歳の男の子・女の子「髪置きの儀」
平安時代の頃は男女ともに生後7日目に頭髪を剃り、3歳頃までは丸坊主で育てるという風習がありました。これは頭を清潔に保つことで病気の予防になり、のちに健康な髪が生えてくると信じられていたためです。3歳の春を迎える頃に「髪置きの儀」を行われていたといわれておりました。子どもの健やかな成長や長生きを願い行う「髪置きの儀」は別名を「櫛置き」「髪立て」ともいい、長寿を祈願するために、白髪を模した白糸や綿白髪を頭上に置いて祝ったとも伝えられています。
5歳の男の子「袴着(はかまぎ)の儀」
平安時代には5~7歳の頃に、当時の正装である袴を初めて身に付ける「袴着(はかまぎ)の儀」を執り行いました。別名「着袴(ちゃっこ)」ともいわれるこの儀式を経て男の子は少年の仲間入りをし、羽織袴を身に付けたとされています。
当初は男女ともに行っていた儀式でしたが、江戸時代に男の子のみの儀式に変わりました。儀式はまず天下取りの意味を持つ碁盤の上に立って吉方に向き、縁起がいいとされる左足から袴を履きます。また冠をかぶって四方の神を拝んだともいわれており、四方の敵に勝つという願いが込められています。
7歳の女の子「帯解(おびとき)の儀」
鎌倉時代、着物を着る際に使っていた付け紐をとり、帯を初めて締める成長の儀式が執り行われていました。これが室町時代に「帯解(おびとき)の儀」として制定され、当初は男女ともに9歳で行われていたとされています。
「帯解(おびとき)の儀」は別名「紐落し」「四つ身祝い」などと呼ばれますが、江戸時代に男児は5歳で「袴着(はかまぎ)の儀」を、女児は7歳で「帯解(おびとき)の儀」の行う形に変わり、この帯解を経て大人の女性へ歩み始めると認められていました。

仏前結婚式
仏前結婚式は新郎新婦どちらかが
その宗派であれば問題ありません。
仏前結婚式とは仏様の前で結婚の報告を行い、誓いを立てる儀式のことです。一方で、神社結婚式は神様の前で報告し、これからの御加護を願う儀式のことです。
仏教の教えに結婚をすると来世まで連れ添うという言葉があります。仏前結婚式は新郎新婦どちらかがその宗派であれば問題ありません。
日本の伝統的な挙式スタイル「神前式」。
神社で結婚式を挙げるということは、お互いに盃を交わす、三三九度の儀(三献の儀)や、玉串拝礼などの儀式を通じて、自分の命、今までの二人の人生を支えてくれた人々、そして二人が出逢えたご縁に感謝し、神様の見守る前で「永遠の愛」を誓い、この先の人生を二人で歩んで行くことを神様に報告するということ。
小さい頃から馴染みのあるお寺やご自宅の仏様の前で結婚式をあげられます。
最近では、馴染みがなくてもお寺で式をあげられるので、信頼できるプロに頼みたい、良心的な価格で式をあげたいという方はぜひ気軽に相談してみてください。